いつかの夢よりも現実はもっと素晴らしい

**********
常に読みかけの本が傍らにあるようにしています。
読む本はかなり節操がなくて、一応は好きな作家もいるのですが、そのとき読んでいる本を読み終えてしまいそうになると、本屋さんで次に読む本を物色したりして、迷いに迷った挙げ句に結局その本屋さんでずいぶん前から平積みにされていて気になってしまっている文庫本を手に取ってしまったり。
で、最近読んで目に付いてた鱗が落ち尽くしちゃった本が、結構話題になったはずの 池谷裕二さんと糸井重里さんの対談を纏めた 「海馬」。
アート(だけではないけれども)がなぜ必要なのか、なんて殊勝なことをたまに考えたりもするわけですが、そのことにこの本の第二章「海馬は増える」の「脳は毎日が面白いかどうかに反応」の辺りが答えてくれていたんです。少なくとも、僕にとっては充分な答えになっていました。
**********

今の時点ではどの程度骨がくっついているのか分からないのですが、負傷して1週間後に撮ったレントゲン写真では順調に治癒の方向に進んでいる模様。
左手が使えなくなるとこういうふうに不便なんだ、という発見はそれはそれで新鮮で、その不便を克服していくのも案外楽しかったりしています。
**********
僕にとって「いつかの夢」ってどんなのだったろう、と考えると、結局それは自分「ひとり」で見ていた夢だったのかな、と。
そして「素晴らしい現実」は、アートの面白さに気付いて、美術館巡りからギャラリーへと鑑賞エリアをシフトしていった頃からたくさんの人々と出会い、たくさんの人とのつながりができて、ぱっと振り返るといつの間にかホントにたくさんの人に囲まれていることを実感できていることなのかな、と。
いろいろと紆余曲折を経て今のブログ 「ex-chamber museum」を始めてから1年ちょっと。その間にレビューした展覧会の数はおそらく500程度はあって、そこにはそれだけのアーティストがいて、ギャラリストやスタッフ、その他にもさまざまな人がいます。そういった方々とのかかわり合いが充実感をもたらしてくれることに、心から感謝しています。
**********

いろんな例えや理論を交えながらの池谷さんの説明と、それを僕らの目の高さに置き換えて、イメージしやすい言葉で表現する糸井さんの感嘆とが絡み合って、楽しく説明してくいれています。
そしてその「刺激」をそのまま勝手にアートに置き換えてみて、自分で膝を叩いてしまったわけでして。
さまざまな作品から得るイメージが、他のさまざまな要素記憶であったり、いっしょに並ぶ作品との空間的な関係だったり、その時の感情であったり、そういったものと脳内で複雑に絡み合うことでイマジネーションが活性化するんだろうな、と。
それは確実に心を豊かにするし、豊かになった心が社会を豊かにするのは疑いがない(と言っていいですよね。いいですよね!)ので、だからアートは必要なんだ、と。
**********

左手の握力がほぼゼロの状態で、だったら左の手や腕のどの部分を使えば能率よく物を持てるか、とか、痛くない角度はどうか、とか。ひとつひとつを無理がない範囲で試しながら克服していくうちに手の具合も良くなってきて。
ずいぶんとポジティブシンキングだな、と自分に若干呆れ気味だったりしますが、まあ、現状をネガティブに捉えて前に進まないでいいような性分ではなく、この程度の怪我で時間を無駄にしちゃうのがもったいなくて。
ちなみに今じゃうっかり「あ、今左手にすごく負荷がかかってる(汗)」といった具合に重たいものを持っちゃったりしてますが、案外大丈夫っぽいです。
怪我して病院で包帯巻いてもらって帰宅してその包帯を取ったときの状況から考えると、人体の仕組みってスゴイと唸らざるを得ないのです。
**********
この「micro」、他にも素敵な曲が並んでいます。
さわやかなアコギのイントロから導かれるポジティブな1曲目「BLUE FLOWERS」、切ない気持ちが淡々としたリズムの上で紡がれていく「ハルニレ」、女性版キセルといった趣の和み系ナンバー「つぶ」などなど。
思わず口ずさみたくなるやさしいメロディがずらりと揃った1枚です。
そしてもうひとつ、演奏も素晴らしいんです。特にドラムがすごい!
**********
・・・とまあ、今回こちらへの記事の依頼をいただきまして、お題はなんでもOK、ということで、こんな感じで仕立ててみましたが、いかがでしょうか。
慣れないことをやってるなぁこの人、と大目に見ていただければ幸いです。
 幕内政治・文
ex-chamber museum主宰。
ギャラリーベースのアートの展覧会のレビューが中心の個人のブログとしては、質はともかく量は世界一かも、と思ってシャレでギネスブックに申請してみようとネットで調べるも、なんだかめんどくさそうだったので一瞬で挫折した。
しかし、それにもめげず、1日1件以上の記事を掲載し続ける日々を送る。
幕内政治・文
ex-chamber museum主宰。
ギャラリーベースのアートの展覧会のレビューが中心の個人のブログとしては、質はともかく量は世界一かも、と思ってシャレでギネスブックに申請してみようとネットで調べるも、なんだかめんどくさそうだったので一瞬で挫折した。
しかし、それにもめげず、1日1件以上の記事を掲載し続ける日々を送る。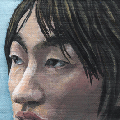 寺嶋悟・イラスト
グラフィックデザイナー
1979年生まれ。福井県出身。大坂デザイナー専門学校グラフィックデザイン科卒業。2001年に共同工房「アトリエ城山」のメンバーに加入(〜2004)。2006年3月よりクリエイティブチーム「ebc」に参加。
寺嶋悟・イラスト
グラフィックデザイナー
1979年生まれ。福井県出身。大坂デザイナー専門学校グラフィックデザイン科卒業。2001年に共同工房「アトリエ城山」のメンバーに加入(〜2004)。2006年3月よりクリエイティブチーム「ebc」に参加。
