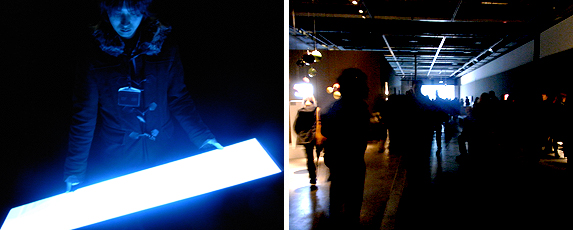美術教育って他の国はどうなの?(トルコ編)

今回は、トルコ人で作曲家・アーティストのシナン=ボケソイに近代化の発展が著しいトルコの現状を聞いてみました。彼はイスタンブールとパリを拠点にして作家活動やコマーシャル音楽などの制作を精力的にこなしています。
1. まずはじめに、トルコの現在のアートシーンを紹介してもらえますか?
これは詳細なレポートを必要とするかもしれない難しい質問ですね。コンテンポラリーアートは最近ギャラリーや展覧会などでみられるようになりました。個人的な見方をすれば、ファインアートや造形作品など観客に対してよい提示をできる機会を持っていると思います。作曲家にとってはそれはとてもうらやましいことなんです。
そして特に20世紀における音楽は他の美術教育に比べて、とても支援が少なかったといえます。コンサートが催されることは少なく、またその中できちんとしたものは更に少なかったんです。
2. 学校で図工や美術の時間はどういったことを学びましたか?
以前、高校や大学で音楽や体育は必修科目でしたが、図工はその学校次第でほぼ選択科目になっていました。音楽の授業では合唱したり、様々な曲を聴いたりというような基本的なことを学びました。また国家の斉唱をすることもとても一般的なプログラムです。それから楽器の演奏ができる生徒は時々コンサートホールで小さなコンサートをする機会をもらいました。私もたくさん演奏したことをよく憶えていますよ。

これは小さいときの家族からのサポートによります。両親からの支援によって子供たちはクラシックの勉強などをすることができます。その一方で、いま楽器をなじみ深いものとするために各年代の若者をターゲットとしたワークショップもあります。そして才能ある人はコンセルバトワール(芸術大学)でそれらの勉強を続けることができます。
4. 日本では美術館やギャラリーは多いにも関わらず、有名なアーティストの展覧会などを除いてあまり人は足を運びません。子供においてはなおさらです。トルコではそういった状況を見受けることはありますか?
こっちではもっとひどいんですよ!
5. 最後になりますが、学校での美術の授業とはどういった役割をすると考えていますか?
教育において、基本的な科目は若い学生に対して確かな成長をするまで受けさせられます。もちろん、それは芸術を科学、歴史、国語や体育から切り離すことはできません。芸術は全ての人にそして、健全な人格形成において必要でしょう。それは学校だけにおいてではなく、家族が子供たちに日々の生活の中で芸術に触れさせてあげ、また支援をしてあげるべきだと思います。
 シナン=ボケソイ Sinan Bokesoy
シナン=ボケソイ Sinan Bokesoy
作曲家、サウンドプログラマ
幼少期からピアノと作曲を学ぶ。1997年にイスタンブール工科大学を卒業し、パリ第三大学にて博士号取得。CCMIX(クセナキス作曲研究所)においてSTOCHOSというアルゴリズム作曲環境ソフトウェアを開発し、各方面より賞賛を得る。他、サウンドとビジュアルによるアートプロジェクトや、オペラの制作にも現在取り組んでいる。





 安岡亜蘭
安岡亜蘭





 名古屋剛志
名古屋剛志




 安岡亜蘭
安岡亜蘭